退職代行を利用した場合、損害賠償請求を受ける可能性は低いものの、退職時の状況によっては会社に損害を与えたとみなされるケースがあります。
この記事では、会社から損害賠償請求される理由や事例、裁判例をもとに、損害賠償請求の可能性について詳しく解説します。
損害賠償請求を未然に防ぐ方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかることは以下のとおりです。
- 損害賠償請求に至る理由と請求事例
- 裁判例から見る損害賠償請求の可能性
- 損害賠償請求を未然に防ぐ方法
退職代行と損害賠償請求の関係性

退職代行を利用した場合に損害賠償請求される可能性は低いものの、退職時の状況によってはリスクも考慮する必要があります。
損害賠償請求の可能性について、以下で詳しく解説します。
退職代行利用で損害賠償請求は稀なケース
会社が従業員に損害賠償請求をするには、従業員の行為によって会社に損害が発生した事実と、その損害と従業員の行為の因果関係を証明する必要があります。
退職代行を利用したという事実だけでは、これらの条件を満たすことは難しいと言えるでしょう。
損害賠償請求の可能性がある退職時の状況
退職の仕方によっては、会社に損害が発生したとみなされるケースがあります。
例えば、以下のような状況です。
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 機密情報の漏洩 | 会社の機密情報を持ち出して競合他社に漏洩させた場合、会社は情報漏洩による損害を請求できる可能性があります。 |
| 引き継ぎ不足 | 突然退職し、引き継ぎも行わずに会社に大きな損失を与えた場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。 |
| 顧客情報の不正利用 | 退職者が会社の顧客情報を不正に利用し損害を与えた場合、損害賠償が認められる事例もあります。(東京地裁平成27年9月30日判決では、約380万円の損害賠償が認められました。) |
これらのケースは、損害額が明確に算出できる場合に限られることに注意が必要です。
退職代行の利用自体が損害賠償の理由になることは稀ですが、退職時の状況や行動には注意しましょう。
損害賠償請求に至る理由と請求事例
会社が従業員に損害賠償を請求するには、損害の発生と従業員の行為との間に因果関係を立証する必要がある点が重要です。
以下では、会社側の立証責任、情報漏洩や引き継ぎ不足による損害賠償請求の事例、そして裁判例から見える損害賠償請求の可能性について説明します。
これらの情報を参考に、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
会社側の損害と因果関係の立証責任
損害賠償請求が認められるためには、会社側が「損害の発生」と「従業員の行為との因果関係」を立証しなければなりません。
この立証責任は会社側にあるため、退職代行を利用したという事実だけで損害賠償請求が認められるケースは稀です。
会社側の具体的な立証責任は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 損害の発生 | 従業員の行為によって、会社に具体的な損害が発生したことを示す必要があります。例えば、情報漏洩による売上減少や、引き継ぎ不足による業務の停滞などが該当します。 |
| 因果関係 | 損害の発生と従業員の行為との間に、明確な因果関係があることを示す必要があります。例えば、従業員が不正に顧客情報を持ち出したことが原因で、売上が減少したというように証明します。 |
| 損害額の算定 | 発生した損害の金額を具体的に算定する必要があります。例えば、情報漏洩によって失った顧客からの売上額や、引き継ぎ不足によって発生した残業代などが該当します。 |
会社側がこれらの立証責任を果たすことが難しい場合、損害賠償請求は認められない可能性が高いです。
情報漏洩や不正競争による損害賠償請求事例
情報漏洩や不正競争は、会社の機密情報を外部に漏洩させたり、競合他社に協力したりする行為であり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
これらの行為は、会社の営業秘密や顧客情報を侵害し、会社の競争力を低下させるため、重大な損害をもたらす可能性があるからです。
情報漏洩や不正競争による損害賠償請求の事例は以下のとおりです。
| 事例 | 概要 |
|---|---|
| 営業秘密の漏洩 | 退職した従業員が、在職中に得た会社の営業秘密(顧客リスト、技術情報など)を競合他社に提供した場合、会社は損害賠償を請求できます。 |
| 競業避止義務違反 | 退職した従業員が、競業避止義務契約に違反して、退職後一定期間内に競合他社に就職した場合、会社は損害賠償を請求できます。 |
| 不正な顧客情報の利用 | 退職した従業員が、会社の顧客情報を不正に利用して、自分の事業のために顧客に営業をかけた場合、会社は損害賠償を請求できます。 |
これらの行為は、刑事責任を問われる可能性もあります。
引き継ぎ不足による損害賠償請求事例
引き継ぎ不足は、退職する従業員が業務の引き継ぎを十分に行わずに退職し、会社に損害を与える行為であり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
引き継ぎ不足によって、業務が滞り、顧客との契約が解除されたり、新規顧客の獲得機会を失ったりする可能性があるからです。
引き継ぎ不足による損害賠償請求の事例は以下のとおりです。
| 事例 | 概要 |
|---|---|
| プロジェクトの中断 | 退職する従業員が担当していたプロジェクトの引き継ぎが不十分で、プロジェクトが中断した場合、会社は損害賠償を請求できる可能性があります。 |
| 顧客との契約解除 | 退職する従業員が担当していた顧客との引き継ぎが不十分で、顧客との契約が解除された場合、会社は損害賠償を請求できる可能性があります。 |
| 新規顧客獲得機会の損失 | 退職する従業員が、重要な顧客との関係を構築したまま退職し、その顧客との関係が途絶えた場合、会社は損害賠償を請求できる可能性があります。 |
ただし、引き継ぎ不足による損害賠償請求が認められるためには、引き継ぎ不足によって会社に具体的な損害が発生したことを会社側が立証する必要があります。
裁判例から見る損害賠償請求の可能性
裁判例からは、どのような場合に損害賠償請求が認められるのか、また、どのような場合に認められないのかを知ることができます。
裁判例を参考にすることで、ご自身の状況が損害賠償請求の対象となる可能性があるのかどうかを判断することができます。
裁判例から見る損害賠償請求の可能性は以下のとおりです。
| 裁判例 | 概要 | 損害賠償請求の可否 |
|---|---|---|
| 東京地裁平成27年9月30日判決 | 退職者が会社の顧客情報を不正に利用し損害を与えたとして、約380万円の損害賠償が認められた事例です。 | ◯ |
| 大阪地裁平成28年3月16日判決 | 退職者が会社の営業秘密を持ち出し、競合他社で利用したとして、約1000万円の損害賠償が認められた事例です。 | ◯ |
| 東京地裁令和2年11月12日判決 | 退職者が会社の顧客情報を持ち出し、自分の事業のために利用したが、会社に具体的な損害が発生したとは認められず、損害賠償請求が棄却された事例です。 | × |
これらの裁判例から、損害賠償請求が認められるためには、会社に具体的な損害が発生したこと、そしてその損害と従業員の行為との間に因果関係があることを会社側が立証する必要があることがわかります。
損害賠償請求は、会社側の立証責任が重く、実際に請求が認められるケースは稀です。
しかし、情報漏洩や不正競争、引き継ぎ不足など、退職時の状況によっては損害賠償請求を受ける可能性もあります。
不安な場合は、弁護士監修の退職代行サービスを選ぶか、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
損害賠償請求を未然に防ぐ方法

損害賠償請求を未然に防ぐには、弁護士が監修する退職代行サービスを利用することが重要です。
弁護士への相談や退職時の状況と行動に注意することで、リスクを最小限に抑えられます。
弁護士監修の退職代行サービスの利用
弁護士監修の退職代行サービスとは、退職に関する法的な助言や交渉を弁護士が行うサービスです。
会社との交渉をスムーズに進め、法的なトラブルを回避するために有効です。
弁護士が監修する退職代行サービスを利用することで、以下のメリットが得られます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的トラブルのリスク軽減 | 会社との交渉を法的に適切な範囲で進めることで、不当な請求や訴訟のリスクを減らすことが可能 |
| 精神的な負担の軽減 | 専門家が交渉を代行することで、自身で会社とやり取りするストレスや不安を軽減できる |
| スムーズな退職手続きの実現 | 退職に必要な書類作成や手続きを代行してもらうことで、滞りなく退職できる |
| 有給消化や未払い賃金の交渉 | 弁護士が会社と交渉することで、有給休暇の消化や未払い賃金の請求を実現できる可能性が高まる |
弁護士監修の退職代行サービスを利用することで、会社とのトラブルを回避し、安心して退職できます。
退職前に弁護士への相談
退職前に弁護士に相談することで、退職に伴う法的なリスクを把握し、適切な対策を講じることができます。
損害賠償請求のリスクを事前に把握し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士への相談で確認すべき事項は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退職の意思表示 | どのように会社に伝えるべきか、伝える時期や方法について助言を受ける |
| 退職理由 | 退職理由をどのように伝えるべきか、具体的な伝え方についてアドバイスをもらう |
| 引き継ぎ | 引き継ぎ義務の範囲や方法について確認する |
| 損害賠償請求のリスク | どのような場合に損害賠償請求される可能性があるか、具体的な事例を教えてもらう |
弁護士に相談することで、法的な観点からリスクを評価し、適切な対応策を講じることが可能です。
退職時の状況と行動への注意
退職時の状況や行動によっては、会社から損害賠償請求されるリスクがあります。
退職前に会社の機密情報を持ち出したり、競合他社に転職したりする行為は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
損害賠償請求のリスクを高める行動として、以下のような例が挙げられます。
| 行動 | 内容 |
|---|---|
| 会社の機密情報の持ち出し | 顧客リスト、技術情報、営業秘密などの会社の重要な情報を、許可なく持ち出す行為。 |
| 競合他社への転職 | 会社の競合となる企業に転職し、会社の営業秘密や顧客情報を利用する行為。 |
| 業務の放棄や引き継ぎの拒否 | 退職前に業務を放棄したり、十分な引き継ぎを行わなかったりすることで、会社に損害を与える行為。 |
| 会社の名誉や信用を毀損する行為 | SNSやインターネット上で、会社や上司、同僚の悪口を書き込んだり、不当な批判をしたりする行為。 |
| 会社の備品や設備を持ち出す | 会社のパソコン、スマートフォン、備品などを、許可なく持ち出す行為。 |
これらの行動は、会社に損害を与えたとみなされ、損害賠償請求される可能性があります。
退職時は冷静な判断を心がけ、慎重な行動を心がけましょう。
まとめ
退職代行を利用した場合の損害賠償請求について解説しました。
退職代行の利用自体が損害賠償の理由になることは稀です。
- 損害賠償請求に至る理由と請求事例
- 裁判例から見る損害賠償請求の可能性
- 損害賠償請求を未然に防ぐ方法
損害賠償請求のリスクを減らすためには、弁護士監修の退職代行サービスを利用するか、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
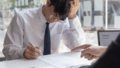
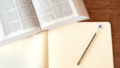
コメント